「こんばんは、カイルさん」
カイルは、彼の髪と同様に射干玉の夜の色を湛えたその双眸を大きく見開いた。眼前には優しく微笑む栗色の髪の少女。その髪に、肩に、粉雪が飾りのように留まり煌いている。外は、まだ雪が止まないらしい。
しかし、カイルが驚いているのはそのことが理由ではなかった。彼女は、この世からは既に消え去った、ここにいてはならない存在のはずだったのだ。彼は思わず、彼女を連れてきたその人を、自らの異母兄である金髪金眼の吸血鬼を振り返った。
カイルの館の玄関。普段は主である彼の魔力で人を寄せ付けないその館も、出来すぎた彼の兄の手にかかれば簡単に侵入できてしまうらしい。突然の訪問に慌てて部屋から飛び出してきたカイルは、そこで彼女―――今は亡き兄の恋人・シェルとばったり再会したのだった。
「あ…兄貴?」
呆然として呼びかける。しかし彼は、あまりにも優れた容姿のその夜の貴族は、どこからともなく現れたメイドに脱いだコートを手渡すと、弟の声が届いているのかいないのか、そのまま優雅な足取りで早々に広間へと姿を消した。
「うそぉ…シェル?」
隣ではケイが、どこか呆けたような、間延びした声で呟いていた。シェルは視線をカイルからケイへと移す。
「ひさしぶりね、ケイちゃん」
「うん! また逢えるなんて思わなかったよ~」
「ええ、わたしもよ」
これはいったいどういうことなんだ?
カイルは頭を抱えてうずくまってしまいたい気持ちを抑え、ぎこちなくシェルに呼びかけた。
「あの…シェル…さん?」
呼び捨てにしようとして、ふと背中に氷のように冷たい視線を感じ、慌てて敬称をつける。しかし、死んだはずのあなたが何故ここにいるのか、などという不躾極まりない質問を、どう発すればいいというのか。そう考えてまごついているうちに、相手の方から話しかけられてしまった。
「あ、そうだ、カイルさん、厨房を貸していただけますか?」
「え? あ、はい、いいですけど…」
まさか頼みごとをされるとは思ってもいなかったので、カイルは反射的に頷いた。それからはたと我に返って、しまった、と思ったが、もう遅い。
「あの…」
「ケイちゃんもいっしょにくる? チョコレートケーキを作ろうと思うの」
「…ちょっと…」
「ちょこれぇと? うん、いくいくーっ!」
「話…聞いて…」
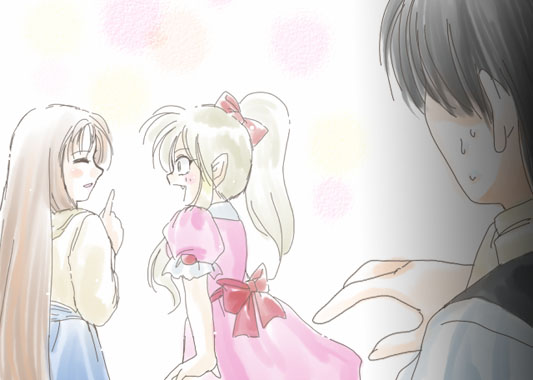
必死に会話しようとするカイルの努力も虚しく、女性二人はさっさと廊下の奥へと消えてしまった。その後姿を見送って、カイルはがっくり肩を落とす。
こうなったら、後はもうラルクに事の次第を尋ねるしかない。しかしまさか兄が、傍若無人で傲岸不遜で天上天下唯我独尊という言葉をそのまま形にしたようなあの兄が、自分の疑問に素直に答えてくれるだろうか?
「はぁ…」
カイルは溜め息をつくと、既にかなり傾いていた肩をさらにがっくりと落とし、とぼとぼとリビングに足を運んだ。そこでは先に部屋に入っていた兄が、何故か館の主である彼よりも寛いで、悠々と紅茶を飲んでいる。
「あのさ…兄貴?」
彼は『だめでもともと』『当たって砕けろ』という言葉の意味をひしひしと感じながら、おずおずと切り出した。どうせ返って来るのは、あからさまな侮蔑か嘲笑に違いない、と思いながら。
しかし、カイルの予想を裏切ってラルクは言った。もっとも、ひどく素っ気無く、ではあったが。
「リドルだ。」
「リドル? …って、あの、ヴァージニティに呼ばれたときに逢った?」
「そうだ」
「あ。じゃあ『あのとき』みたいに? でも…なんで?」
訳が分からないといった顔の弟に、彼は溜め息をついて事情を説明した。
「昨夜、街から街へ渉る途中に、突如として彼女達の館が現れたのさ。今年は雪が深いだろう? よくは知らないが、今宵二月十四日というのは人間達にとって大切な日らしいからな。気を利かせてくれたのだそうだ」
少しだけ忌々しげな口調。先夜、風花の舞い散る中に忽然と姿を見せたその屋敷に、ラルクは見覚えがあった。ヴァージニティとリドルという名の二人の女性と、この冬と同様に雪がひどく深かったある夜のことが否応なく思い出され、まさかと思っているところにやはり彼女が、シェルが現れたのだった。
そのときのことを思い起こすと、同時にリドルの嫌味ったらしいほど恩着せがましがった声が、ラルクの脳裏に蘇った。
『ふっふーん。二月十四日っていうのはね、愛し合う恋人達の記念日なのよ。この冬はまだ長そうだし、まだまだ雪解けには遠いみたいだし、今年だけトクベツに、シェルと一緒に過ごさせてあげようと思ってね!』
彼女はやたらと『特別』という言葉を強調してそう言った。
「そしてこう付け加えたのさ。『どーせあなたは家なんて持ってないんでしょうから、ここから出たらすぐにカイルの家の前に着くようにしておいてあげるわ。そこでシェルにチョコレートでも作ってもらいなさいよ』と、な」
「俺の家の前にって…」
あまりのことにあんぐりと口を開けたまま絶句したカイルから剥がした視線を窓の外へと向けて、ラルクは未だに止むことを知らない白雪を見遣った。
「彼女達は我々の『管理人』のようなものだと言っていたからな…ある程度のことは、思うが侭に出来るらしい」
その言い様は相変わらず刺々しかったが、その切っ先が確かに和らいでいるのを、カイルは見逃さなかった。
―――ある程度。
ラルクには充分すぎるほどよく分かっているのだ。そのおかげで彼が、命あるうちはもう二度と逢うことのないはずの彼女と言葉を交わすことが出来たのだということを。
(兄貴…)
思わず心の中で呼びかける。カイルとて、大切な存在はいる。だが彼は、それを失うようなことには、幸いなことになってはいなかった。ラルクが今どんな想いでいるのかは、だから彼には分からない。
カイルは何も言えず、メイドが運んできた自らのカップを持ち上げて静かに紅茶を啜った。が、ふと思いついて顔を上げる。
「そういや、さ。何で、チョコレートなんだ?」
「そこまでは知らんよ。」
ラルクは再び素っ気ない口調に戻って答えた。それに安堵したカイルは、その後、ラルクが僅かに思案顔になったことに気づかなかった。
(…そういえばリドルは別れ際、シェルに何を耳打ちしていたんだ?)
「愛の告白ぅ!? …人間って、変わったことするんだね~」
一方、厨房では、二月十四日・聖バレンタインディにまつわる話をシェルから聞いたケイが、素直な感想を述べていた。
「そうね。でも、こういう機会って、そうそうないんじゃないかしら?」
ちょこっと首を傾げて、シェル。
チョコレートケーキはちょうど今、焼き上がったところだった。後は切り分けてお皿に盛り付けて、最後にそこに粉砂糖をまぶせば完成する。シェルはそっと、まだ熱々のケーキにナイフを入れた。
「ケイちゃんだって、カイルさんにはっきり言うときは躊躇ったりしない?」
「あ…うん…そう、かも…」
「でしょう?」
4つに分けたケーキを、ひとつずつ、ケイが用意しておいたお皿に乗せた。シェルはさらさらと、そこに今夜の粉雪のような砂糖を振りかける。ふっくらとしたチョコレートケーキは、まるで白粉をはたいたように真っ白になった。
「ほら、出来上がり」
「わーい、できたできたーっ! カイルーっ」
銀のお盆に自分の分とカイルの分の、二つのケーキとフォークを乗せると、ケイはシェルを待ち切れずに厨房を飛び出した。置いてけぼりをくらったシェルは、それでも微笑んでそれを見送る。そうしてケイの足音がすっかり聞こえなくなった頃、何かを思い出したようにぽん、と手を打った。
「いけない、すっかり忘れてたわ」
そう言いながらも決して慌てたふうもなく、彼女はポケットから小さな壜を取り出した。