「よ…夜這い!? カイルさんっ! そんなこと本気で言ってらっしゃるんですかっ!?」
耳をきーんとつんざくような悲鳴に近い叫び声を上げて、ラルクはカイルの提案を却下した。カイルの屋敷の広間。ケイとシェルはいない。カイルは、ラルクのその声に驚いて、慌てて彼の口を手で塞いだ。
「おれだってそんなこと言いたくない! もしもあんたに記憶が戻って、このことを憶えていられたとしたら、おれは兄貴に半殺しにされるに決まってる! でも仕方ないだろう? シェルは訳ありで、今日をいれてあと三日しかここにいられないんだ!」
「むぐ…もご…」
反論しようと必死になってもがくラルクをさらに強い力で押さえつけてカイルは言う。
「それとも、あんた、他に何か手があるっていうのか!?」
「…うっ」
その言葉を聞いて、ラルクはようやく大人しくなった。カイルは彼の口を押さえていた手を放して、諭すように話し始める。
「いいか? シェルがここにいられるのは、どう足掻いてもあと三つの夜と昼だけなんだ。そのあとは、いつこっちに来られるかも、いやこっちに来られることがあるかどうかさえ分からないんだぜ!?」
さすがに記憶喪失の彼に、
『記憶を失う前のあんたの恋人で、今あんたが惚れてるシェルは、実はもうこの世にはいない人なんです』
とは言えず、そこは適当に話をはぐらかし、カイルは続けた。
「それともあんたは、おれやケイに一生面倒を見てもらうつもりなのか!? 記憶を取り戻すことを投げ出して!?」
「そっ…それは…でも夜這いだなんて…!」
「でもも何もない! あんた、彼女に惚れたんだろ!?」
「それはっ…だって…雪明りに照らされた彼女の色白の顔があまりにも可憐でしたから…その長い睫毛の影が落ちた薔薇色の頬も…」
かーっと耳まで赤く染めてごにょごにょと言い張るラルクに、今宵何度目かの吐き気をもよおしながら、それでもカイルは必死にそれに耐えた。
「だから! あんたが何とかして彼女とキスしなきゃ、あんたは元には戻らないんだって!」
そう言ってカイルは髪の毛を掻き毟る。
(この作戦会議のためにわざわざケイに頼み込んで、シェルを厨房に連れて行って今日のおやつを作ってもらってるってーのに、どーしてこうも話が進まないんだ!)
カイルの計画を聞いたケイは最初、心底嫌そうにしていた。彼女はシェルに好意を抱いているから、嫌がるのも無理はないだろう。しかしカイルの、
『じゃ、兄貴がずーっとあのままでもいいのか?』
という一言にびくっと身体を震わし、無言でこくこくと頷いたのだ。
「なぁ! 頼むよ…」
「…分かりました」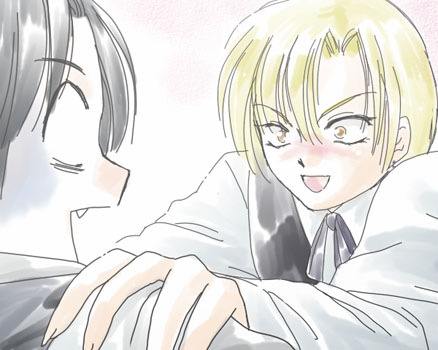
すがりつくように呟くカイルを見かねたのか、遂にラルクは頷いた。しかしそこには、まだ続く言葉があった。
「わたしが、この三日で、彼女の心をつかめばいいんですね!」
「…え゛?」
予想外の台詞に目を丸くするカイル。それに気づかず、ラルクはがしっとカイルの両肩を押さえていった。
「彼女は、記憶を失くす前のわたしの恋人…ひどく気は引けますが、彼女に罪悪感を感じずにくちづけを交わすにはこれしかありません! だから…」
記憶喪失になって、ラルクがやたらと人のいい性格になっていたのには気づいていた。しかし、これは…!
「だから…?」
嫌な予感を抑えることが出来ずに、ついカイルは聞き返してしまった。それを聞いたラルクが勢い込んで頼み込んでくる。
「お願いです、カイルさん! 女性の口説き方を教えてくださいっ! あなただけが頼りなんですっ!」
がんっ!
強く頭を殴られたようなショック。涙を溜めた金の瞳に見つめられ、カイルはどさっとその場にくずおれた。
「…はい、何か?」
シェルは、しどろもどろといった口調で自分に話しかけてきたラルクの方を振り返った。ケイとカイルは、先刻シェルが厨房で焼き上げたクッキーをかじりつつ、こそこそとソファの陰に隠れてその様子を見守っている。
「ねー…ほんとーにうまくいくのぉ?」
とっても心配そうなケイの声に、カイルは肩を落としてげんなりと答えた。
「頼むから、おれに訊かないでくれ…」
ちょうどカイルが倒れた後すぐ、厨房から女性二人が戻ってきたらしい。ケイに介抱されて意識を取り戻したカイルはケイに状況を説明し、こうして二人をくっつけようとしているわけだが…
(もう嫌だ…何もかもがイヤだ…)
カイルがその心の中で大量の涙を流しつつ二人の様子を窺うと、シェルに見つめられただけで、ラルクはまたまた顔を真っ赤にしているところだった。
(ほんとーに…うまくいくんだろーか…)
半ば諦めかける。と、そこに突然、
「カイルさんっ!」
「うわぁッ!」
「…想いのたけを伝えるのには、どうするのがいいんですかっ?」
いつのまにかソファの後ろに回り込んだらしいラルクが、真剣そのもの、といった表情でカイルを見つめていた。
「どう…って、素直に直接…が一番いいんじゃない?」
さすがに固まってしまったカイルを気遣ってか、ケイが横からさっと助け舟を出す。しかし、ラルクにはその、直接、というのが難しいらしかった。
「だって、彼女の瞳を見ただけで胸がどきどきして、心臓が破裂しそうで…」
シェルはというと、事の成り行きが分かっているのかいないのか、相変わらずの微笑みでこちらを眺めている。
「それは…たとえば…」
ケイは何もいい例が思い浮かばず口を閉ざしてしまう。と、とうとうカイルが声を荒げた。
「あーもう! そんなんいつもの兄貴みたいに、歯が浮くような気障ったらしい台詞をいくつも並べればいーじゃないか!」
頭に血が上ったせいで混乱しているのか、記憶を失う前と後の兄が頭の中でごっちゃになってしまったらしい。しかし、それに気づく余裕すら、今の彼にはなかった。
「『まさか、僕がこんな気持ちになるなんて…』とか、『僕を、信じて』とか…木の根につまずいた彼女を抱き上げて『この方がよっぽど安心だ』って囁くとか…『僕を一人にしないで』とか…! …と、とにかくいろいろあるだろ、レパートリーは!?」
言っていてさすがに恥ずかしくなったのか、最後の方は適当にごまかす。
「ええっ!? そんな…あの…えっと…言葉を…使うん…ですか?」
今度は照れから真っ赤になったラルクが問いかける。
「だって…そんな…どんなふうに言えばいいんですかっ!?」
「えっ? そっ…それはっ…」
戸惑ってしまったカイルに好機を見て取ったのか、いいことを思いついた、というようにやたらと勢い込んで付け足した。
「そうだ、ケイさんはカイルさんの恋人なんでしょう? 今ここで、試しに彼女に向けて言ってみてください!」
あまりといえばあまりなラルクの言葉に、
「なッ!?」
カイルはその顔を、先程のラルクに負けず劣らず赤くした。
(そんなこと…!)
口が裂けても言えるか、とケイを振り返り、思わず絶句する。
「カイルぅ…」
ほんのりと頬を桜色に染めて、期待に満ちた潤んだ瞳のケイがそこにいたのだ。
「だ・か・らーッ! 違うだろッ!? あんたが! 彼女に! 言うんだってば! ケイも、頼むからつられないでくれ!」
ラルクの胸倉をつかんでゆさゆさと揺さぶりながら、カイルはものすごい怒気を含んだ声で、一言ひとこと句切るように叫んだ。最後の言葉は振り返り、真っ直ぐに自分を見つめるケイに向かって吐き出す。
「…あらあら、記憶を失くしても仲がいいのね、カイルさんとラルク」
彼らのやり取りをずっと見守っていたシェルが、見当はずれの感想を溜め息とともに呟いた。それが聞こえたのか、カイルはまたがっくりとうなだれた。